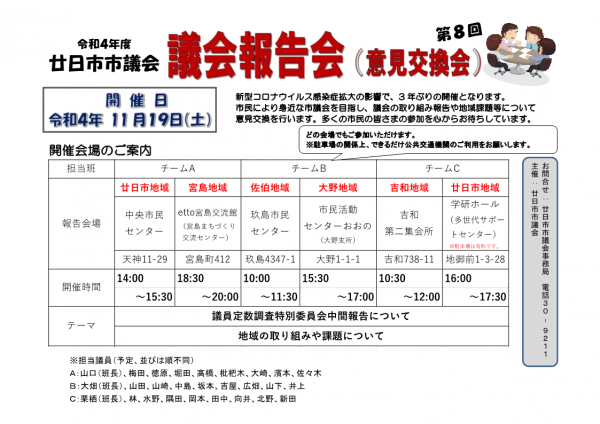本文
令和4年度 議会報告会
頂いたご意見などへの回答
議会報告会で参加された皆さまからいただいたご意見などに関しては、関係する所管の委員会へ振り分け、
各委員会で取り扱いに関して検討し、次のように整理を行いました。
委員会で調査・検討するもの
| 委員会 | 市民意見など |
|---|---|
広報広聴 特別委員会 |
難しい言葉は不要、わかりやすい言葉で説明してほしい。 |
| パワーポイントだけではなく、文字が見えにくいので資料も配布してほしい。 | |
| 難しいテーマであれば、質問に答えられる専門的スタッフが必要では。 | |
| 説明資料の専門用語の使い方に対する調整。 | |
| パワーポイント資料の配布に対する調整。 | |
| アンケート結果など、アナログな対応でよいので資料が欲しい。 | |
| 画面だけでなく、今回の資料を配ってほしい。 | |
| 意見交換の時間が少ない。 | |
| 質問時間の制限が必要。 | |
| 流域治水に関して聞きたかったが時間的余裕がなく聞けなかった。 | |
| 市民意見を聴くよい機会であるが、周知不足の解決と、意見交換会の在り方が課題。(なるべく多くの意見を聴き出せるよう、進行管理や、開催方法(少人数に分ける)などの工夫が必要) | |
| この様な意見を言えるのであればもっと早く日程を教えてほしかった。 | |
| スクリーンの文字が小さく見えなかった。資料が必要。 | |
| 若い世代にはSNSを活用するなど、若い世代が参加しやすい工夫を。 | |
| 議会が可視化されていない。若い人は時間に余裕がない。もっと若い世代に働きかけを。 | |
| 11月は忙しいので開催時期を変えてほしい。 | |
| 忙しい人は参加できないので、日時を変えて複数回開催してほしい。 | |
| 宣伝が足らないのでは。宣伝カーで「ひんぱんに」走らせる。 | |
| 議員の方が手分けして地域を見て回られ、地域の声を聞ける。 | |
| せっかくの機会ですので、もう少し参加があればと思います。宣伝の仕方。 | |
| 議会や議員の活動が見えない。広報さくらに議員の通信簿を載せてはどうか。 | |
| 議会報さくらは、特定地区の意見ばかりで全体のことに関して意見を出すべき。 | |
| 議会に関しては、コミュチャンネルなどで中継すべき。 | |
| 文教厚生 常任委員会 |
佐伯高校に地元が入れなくなった。定員の枠は増やせないのか。 |
執行部へ回答を求めたもの
| 委員会 | 市民意見など | 回答 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 総務 常任委員会 |
大雨の際、防災無線の音は電車の音もあり聞こえない。 地御前は聞こえないとの声を聞くが、場所によって聞こえすぎるがどうなのか。 |
防災行政無線により情報発信した際には、「放送内容が聞き取りにくい」、「聞こえない」といった意見をいただいている。令和2年度に調査を実施した上で、令和3年度に屋外拡声子局の新設やスピーカーの増設、高性能スピーカーへの取替えを行うなど、音達状況の改善に取り組んでいる。 しかし、防災行政無線の音達範囲が重なると、音が重なって聞き取りにくくなり、音達範囲が重ならないようにすると、今度は音達範囲と音達範囲の境目の音が小さくなって聞こえにくくなる。また、防災行政無線は地形や天候の影響を受けやすく、さらに近年の住宅は気密性が高いことなどから、すべてのエリア、世帯に同じように情報を伝達することには限界があると考えている。 このことを踏まえ、緊急時の情報発信に関しては、防災行政無線だけではなく、フリーダイヤルや緊急速報メール、安全・安心メール、市ホームページ、FMはつかいちによるラジオ放送、廿日市市LINE公式アカウント、避難誘導アプリ「避難所へGo!」など、さまざまな伝達手段により発信することで、避難すべき人がいずれかの方法により避難情報を得て、迅速・的確な避難行動につなげることができるようにしている。 市民の皆さまには、防災行政無線から警報音、サイレンが聞こえたときには、テレビやラジオ、携帯電話・スマートフォンなどで最新の情報を入手し、落ち着いて避難行動につなげていただきたいと考えている。 |
危機管理課 |
| 防災無線対策として、廿日市市版Jアラートのような携帯を活用した情報伝達はできないのか。 | 本市では、携帯電話・スマートフォンを活用した緊急速報メールによる、プッシュ型の緊急情報の伝達を行っている。そのほか、登録制の安全・安心メールや廿日市市公式LINEアカウント、ひろしま避難誘導アプリ「避難所へGo!」なども用いて情報伝達している。 | ||
| デジタル化の時代に従って、もっとデジタル化・AI化を推進すべき。 | 本市では地域社会全体がデジタル化の恩恵を享受できるまちづくりを推進するため、令和4年4月に廿日市市DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進計画を策定した。計画では、「デジタルの力で豊かな暮らしとまちの未来を創造する」を基本理念として、RPA やAI などデジタル技術を活用した取組を行うことにしている。 一例を挙げると、書かない・待たない・行かなくてもいい行政サービスの実現を目指した取組として、市LINE 公式アカウントを活用したスマート申請(オンライン申請)の拡充を進めている。 |
デジタル改 革推進課 |
|
| 建設常任委員会 | 昔は水路は浚渫していたが、今は暗渠になっているところが多いが対応は。 | 流下能力に影響のある箇所に関しては、必要に応じて管渠浚渫を実施している。 | 維持管理課 下水道建設 課 |
| 5区から4区の交通渋滞の解消 | 大野5区から4区への交通渋滞は、国道2号の交通渋滞により、渋滞を避け生活道路への流入が原因と考えている。 国道2号の抜本的な渋滞対策に関しては、道路管理者である国へ要望しているものの未だ方針が示されてない事から、引き続き、強く要望している。本市としては、国道2号の交通渋滞の要因のひとつである観光シーズンにおける宮島口地区の観光交通と通過交通の円滑化が図れるよう、国道2号と宮島口旅客ターミナルを結ぶアクセス道路や市道赤崎14号線などのハード整備を行うとともに、うろつき車両への交通誘導やパークアンドライドの推進、満空情報配信などのソフト施策を進めることで、国道2号の渋滞緩和を図り、5区から4区への生活道路への流入を抑制し、交通渋滞の解消を目指したい。 |
宮島口みな とまちづく り推進課 |
|
| 沿岸部の高校にも通えるように、通学用の直通便をつくれないか。 | 中山間地域においては、児童・生徒の身近にある学校の存続支援が必要であり、吉和学園、佐伯中学校と佐伯高校へ通学できることを最優先に、吉和、佐伯間の吉和さくらバスの時刻を設定している。現在の利用実態として、吉和地域から佐伯高校へ通学している生徒や、佐伯地域から吉和学園へ通学している児童生徒、また、朝の通学時間帯に、通院で利用されている。 沿岸部の高校への通学を考える場合、高校の場所によって所要時間が異なることから、それぞれの学校の始業時間に合わせた運行は難しいと考えている。 |
交通政策課 |
執行部へ報告したもの
| 委員会 | 市民意見など |
|---|---|
| 総務 常任委員会 |
市職員の残業代削減に向けて監視強化を。22時過ぎたら完全退庁を。 |
| まるくる大野は、イメージ図で40万人集まる、と絵や図面で言われても、こうするから40万人集まる、ということを言ってほしい。 | |
| 議員の定数を減らすより役職が多すぎる職員の数を減らしてほしい。 | |
| 宮島にタックスフリーの事務所を設けたらどうか、検討してもらいたい。 | |
| 独身者の住む家がないので、そういう施設をつくると若い就労者が増えるのではないか。 | |
| 環境産業 常任委員会 |
宮島で、イノシシやシカが、また、それらに関しているマダニが観光客に何らかの被害を及ぼした時の補償は。宮島訪問収入を使えないのか。G7のお金をうまくやって、観光に来られる方の安全性を担保してもらいたい。登山道の樹木を、谷側は3~2メートル、山側は3~4メートル伐採すればマムシやマダニがいなくなり眺望も良くなる。絶好のチャンス。 |
| 水と緑のまちと言われるようだが、山は荒れているのがけっこう目につく。高齢化で山に入る人が少なくなり、木は輸入する。大野でもだいぶ山が荒れてきている。県道42号 ごみ、コンビニの食べかすが捨ててある。カラスがつついて目をそむけたくなるような状況。テレビや小型冷蔵庫も捨ててある。ゴミ袋を有料にしたとたん顕著になりだした。 | |
| イノシシにハクビシンが増えている。 | |
| 県道沿いのごみ不法投棄 | |
| 鳥獣被害対策 | |
| 働く場所が少ないのも課題である。 | |
| 建設 常任委員会 |
宮島口の松大船から降りると階段があり、動線が悪いので、サミットのお金で改善してもらいたい。 |
| 水道広域連合の件は、他県とも統合を考えスケールメリットを拡大すべき。 | |
| 車に乗れなくなったら動くことができない。バスもデマンド交通も来ない。生活できない。 | |
| 電動車いす(シルバーカー)で動こうとすると、歩道がきちんとできていないので危険。ゴルフ場の近くで、非常に整備の難しいところ。ダンプや大型車が良く通る道なので普通車で出るのは相当気をつけないといけない。大型車は、ほとんどセンターラインオーバーに近い走り方をする。解決できればと思う。 | |
| 高齢者の外出支援 | |
| さくらバスの沿岸部の高校に通えるダイヤでは、朝は早すぎ、夕方は時間待ちする必要があるなど現実的でない。 | |
| 空き家も課題である。住民票をもって別荘に移り住む人もいるが、子の世代に変わって売りに出す人もいる。 | |
| 文教厚生 常任委員会 |
冬場の雪の多い時、その辺(佐伯中心地や、玖島中心地など、交通便利なところの意)に仮に住まわしてもらえる寮のようなものを考えないといけないのでは。 |
| 冬季に高齢者が安心して過ごせる寮のような施設 | |
| JA広島総合病院の耐震性のない東棟の今後の活用方法は。 | |
| JA広島総合病院の内視鏡検査などで麻酔使用の選択が可能となるよう、もっと患者の要望を聞くように伝えてほしい。 |
その他(議会・市では対応できないもの/議会報告会で回答済み/一般質問実施済み など)
| 委員会 | 市民意見など |
|---|---|
| 環境産業 常任委員会 |
廿日市市にも観光大使をつくってほしい。 |
| 建設 常任委員会 |
二重原地区開発に伴う排水対策はどうなっているのか。 →35年前の山陽道高速道路設置工事の時、土砂が流出し可愛橋が壊れた。土地の価値が下がるので、我々の土地を浸水地区にしてほしくない。 |
| 二重原地区開発に伴う排水対策はどうなっているのか。 →開発工事で木を切ると土砂が流され川がつぶれる可能性がある。工事着手前に調整池をつくってほしい。 |
|
| 開発工事前に議会で議論はされたのか。 →自然を残さない開発をなぜするのか。 |
|
| 二重原地区開発工事に伴う調整池の設置に関して | |
| 昨年の大水浸水時、ポンプが故障したのか。また、今後の対策はどうなっているのか。 | |
| 南道路の話を聞いたが、地御前には行き止まりやUターン、線路での立ち往生など、袋小路にしない対策を望むがどうか。 | |
| 広報広聴 特別委員会 |
傍聴者のアンケートを発表してほしい。 |
| 総務 常任委員会 |
まるくる大野 立派なものができている。図書館はつぶす必要あったのだろうか。もったいない、度を過ぎているのでは。建物に耐震性もあるのになぜなくすのかどうしても理解できない。 |
| グローバル社会の中で、老人ホームなど外国人が安い賃金で働いている。若い人に介護してもらわないといけない。議員がどういう見解を持っておられるか。派遣会社が市にも入っている。派遣や非正規で仕事に入ると、生活に不満ができ、虐待などに繋がることも。 | |
| 2023年のひろしまサミットに関連し、警察署から山手に入る道が悪いので整備してほしい。国から7,400万円も交付されるのなら、紅葉谷と桟橋前に使ってほしい。 | |
| (報告パワーポイント)「人を育む」とか子どもを大切にする、というようなことが書いてあるが、どこのことだろう?現実は…。過疎で人を呼び込むと言うが、子どもを育てるところがないところに人は来ない。(保育園や学校がない) | |
| 高齢化が進んでいるが、将来どう対処していかれる思いなのか。限界集落がいっぱいある。 | |
| 文教厚生 常任委員会 |
大野福祉センターは3月をもって廃止の方向と聞く。解体か売却か、とのこと。佐伯にはさいき文化センター、廿日市にはさくらぴあがある。大野福祉センターは文化施設並みの扱いであった。なくなるのは困る。さくらぴあや、さいき文化ホールへ行けと言われても無理。まるくる大野を使ったらどうかと言われるが、文化的な要素で使うのは無理。 |
| まるくる大野に関して、子育て支援を言われたが、逆に年寄りは最期まで元気でおりたい。そのためにいろんなところで活動することは重要。音を出すところ→大野福祉センターがあるが、今、ライトもカーテンもなく台しかない。踊りをやっている方の発表の場などどうするのか。廿日市市全体の問題だと思う。高齢者の活動ということに共感していただけるか。 | |
| 大野地域における文化芸術発表の場の確保策(大野福祉保健センターの今後の取り扱い) | |
| 佐伯高校以外の高校は通えず、下宿や寮ということになる。市街地に専用の寮を整備できないのか。 |